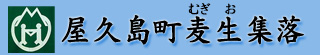このページでは、麦生集落の民家に伝わる正月飾りを写真で紹介しています。
民家のお正月飾り 平成24年(2012年)1月1日
門松やしめ縄、鏡餅など、麦生集落の民家に伝わるお正月の飾りを大山武盛さんの本家で撮らせていただきました。

左から、船の神様、床の間の神棚、ご先祖様の仏壇

左の鏡餅は『二十三夜様』、右は『家(や)の神様』。二十三夜様とは麦生を護っている神さんで「お産の神さん」。

船の神様。これらの正月飾りは、潮が満ちてくる時間に飾ります。潮が引いていくときにはしません。

屠蘇器の左は焼酎、右は地酒。皿には刺身12切れ、香の物12切れ。31日の晩に戸主→妻→子の順に食べ、神様に感謝と無病息災、豊作を祈願します

台所の荒神様にも、鏡餅とユズリハ、雪松を飾ります

門松は、シイノキ。松を飾る家もあります。足元はマテの木(どんぐりの木)の割り木を5本組みます。しめ縄は人が腰をかがめてくぐる位置に垂らします。

供え物の里芋は小芋がたくさんつくことから、子孫繁栄の象徴として、ダイダイは「家が代々続く」との願いをこめて供えます

供え物。半紙の上にダイダイをのせ、雪松、ユズリハ(いずろは)、ウラジロ(もーむき)を刺して立て、昆布を巻いたもの。

左写真のつづき。半紙の下の重箱に一升の米を入れます。この米は20日に食べます

鏡餅の下には、ウラジロ(表向きに置きます)と、ユズリハを一枚置きます

雪松。昔はマツの葉に脱脂綿を乗せ、雪に見立てたそうです。今は白い粉を糊でつけます

しめ縄飾り。ワラのタレは外側から、7.5.3.5.7本です。真ん中には、マツ、ユズリハ、ダイダイをとめてあります
1月2日の朝に行われる行事について大山さんが話してくれました。
2日の早朝、床の間の神棚に供えた重箱のお米を持って井戸に水を汲みにいきます。井戸の周りにそのお米をまいて、柄杓(ひしゃく)で水を汲むしぐさをして唱えます。
『年の初めて 水をむくゆるには 黄金のしゃくに 黄金のおけ 水を汲まずに米(よね)を汲む』
これを3回となえて、杓(しゃく)で水を汲み桶に3回入れます。この水を家に持ち帰り炊事に使います。
大山さんは山仕事をしていたので、2日の朝にもう一つの行事をしました。
戸主である大山さんが斧をかついで山に入り、『年の初めに木を伐るには よーじのたかだ よーじのたかだ よーじのたかだ』と言って、斧を3回、木に打ち込みます。
同じ2日の朝、畑にも行きます。畑には夫婦で行きます。畑にクワで溝を3箇所切り、お供えした重箱のお米、お神酒、塩、を置き、今年も豊作であるようにと祈願します。
これらの行事は、大山さん(82歳)自身が自分の父親のすることを見て覚えたそうですが、もう2、3年前より行っていないそうです。
2日の早朝、床の間の神棚に供えた重箱のお米を持って井戸に水を汲みにいきます。井戸の周りにそのお米をまいて、柄杓(ひしゃく)で水を汲むしぐさをして唱えます。
『年の初めて 水をむくゆるには 黄金のしゃくに 黄金のおけ 水を汲まずに米(よね)を汲む』
これを3回となえて、杓(しゃく)で水を汲み桶に3回入れます。この水を家に持ち帰り炊事に使います。
大山さんは山仕事をしていたので、2日の朝にもう一つの行事をしました。
戸主である大山さんが斧をかついで山に入り、『年の初めに木を伐るには よーじのたかだ よーじのたかだ よーじのたかだ』と言って、斧を3回、木に打ち込みます。
同じ2日の朝、畑にも行きます。畑には夫婦で行きます。畑にクワで溝を3箇所切り、お供えした重箱のお米、お神酒、塩、を置き、今年も豊作であるようにと祈願します。
これらの行事は、大山さん(82歳)自身が自分の父親のすることを見て覚えたそうですが、もう2、3年前より行っていないそうです。
写真のページはこの他に、神社お寺の行事、年中行事(鬼火焚き他)、二十三夜祭、娯楽行事(運動会・大祭)、奉仕作業があります。